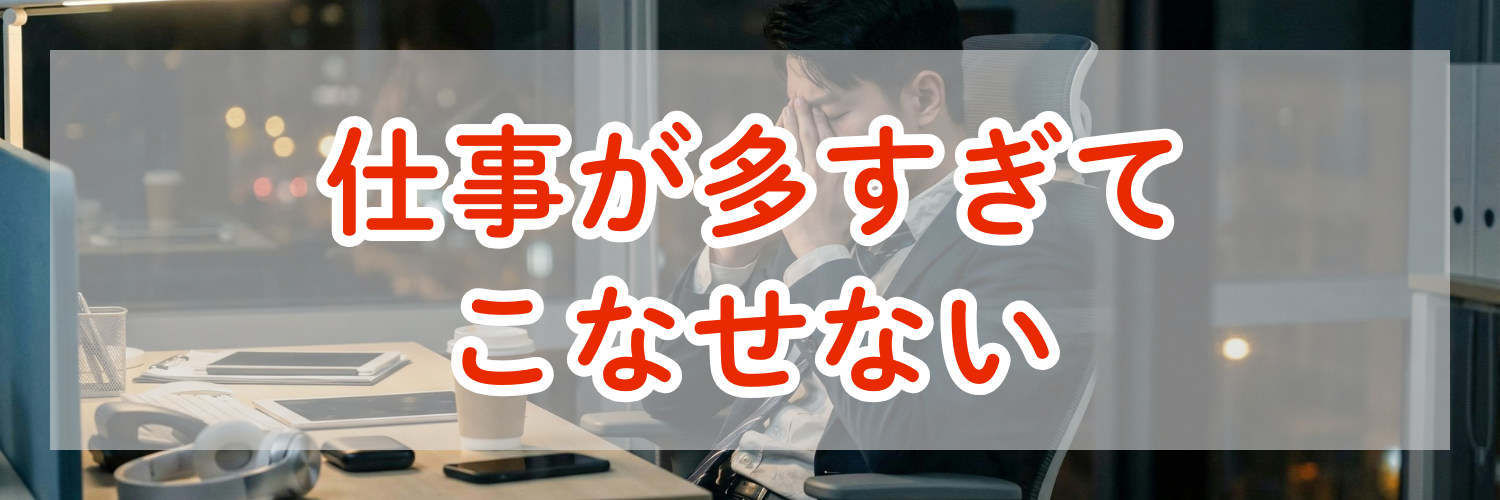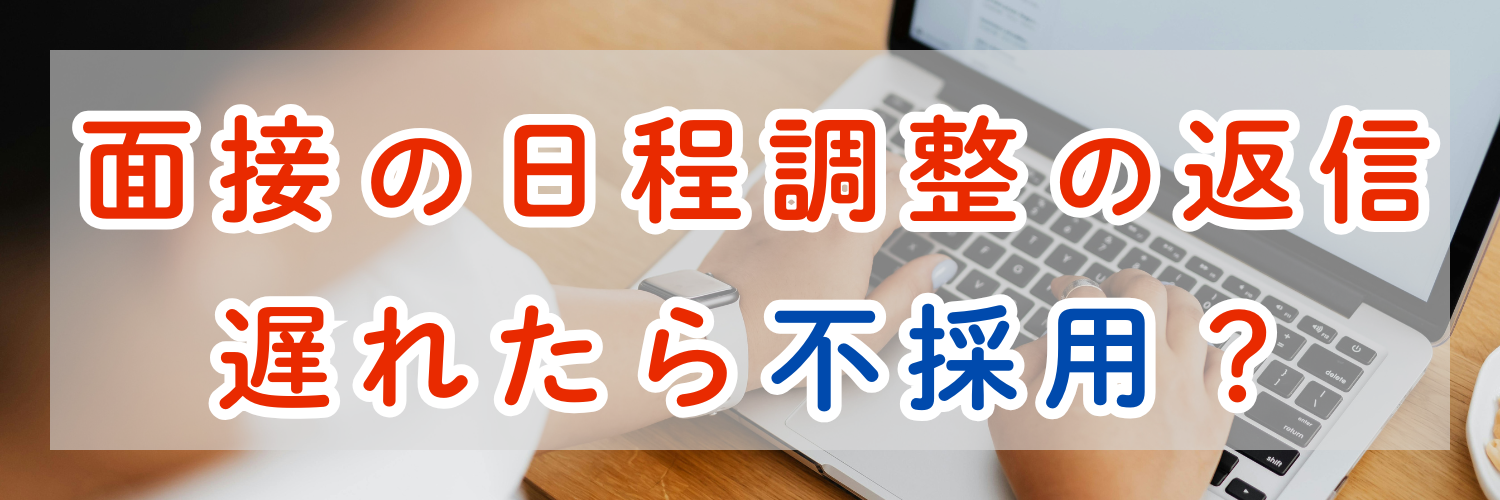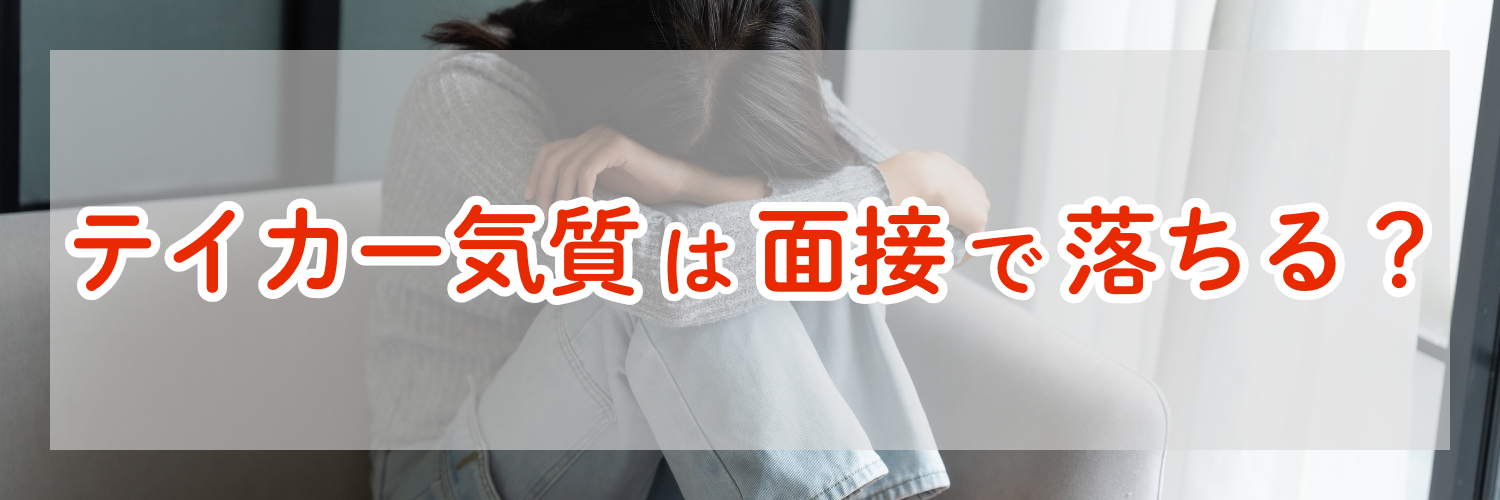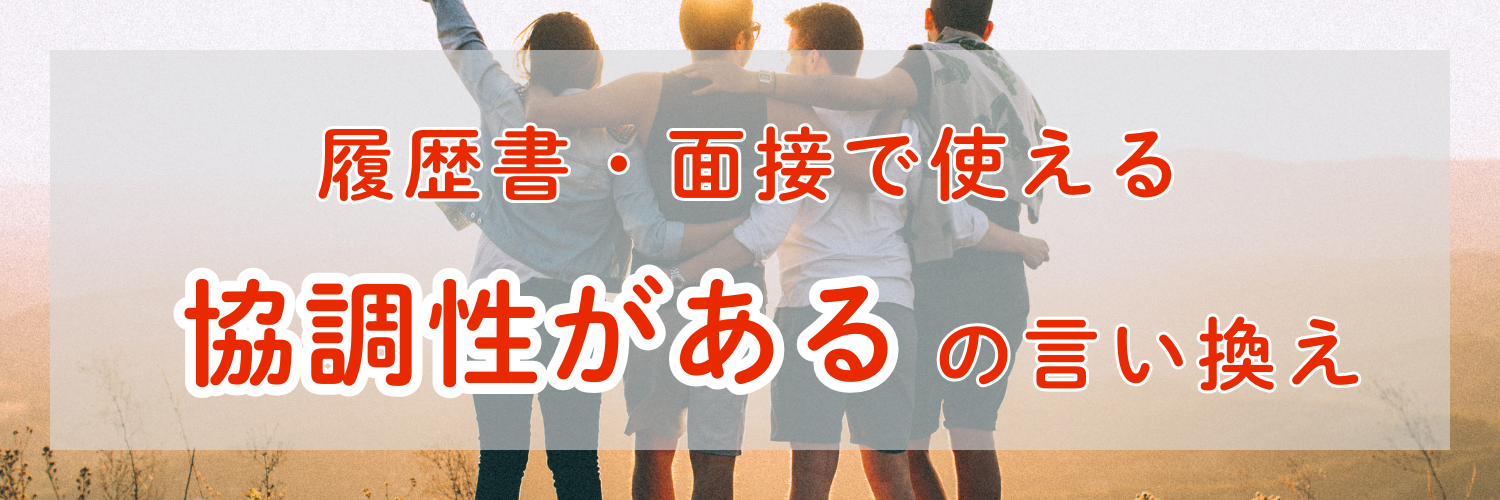転職アカホン講座
ビジネスにおけるバディ制度のデメリットとは?不安を安心に変える制度の理解と活用ポイント

- バディ制度とは?
- 新入社員・留学生の受け入れで活用される背景
- 社員が業務の中でどう関わる?バディの基本的な活動内容
- メンター制度やOJTとの違いは?役割や目的の違いを整理
- メンター制度との違い|心理的支援と業務支援の役割差
- OJTとの違い|日々の仕事の中での指導との違い
- なぜバディ制度を設けるのか?企業側の目的とは
- 定着率向上や早期戦力化への期待
- 社員同士のコミュニケーション促進・組織活性化
- バディ制度を導入するデメリットとは?注意すべき4つの課題
- バディ側の業務負担が重くなりがち
- 相性による影響が大きい
- 属人化・形骸化のリスク
- やらされ感が生まれる
- バディ制度の効果を最大化させるための運用の工夫
- バディ制度の目的と役割を明文化する
- 定期的な面談・フィードバックで孤立を防ぐ
- 上司や教育担当と連携したトライアングル支援
- バディ制度を導入している企業
- 株式会社LITALICO
- 株式会社ラクス
- Sansan株式会社
- 共通する成功ポイント
- 不安を感じたらどうすればいい?制度との付き合い方と企業選びの視点
- 「同期がいない=不安」と決めつけない考え方
- 信頼できる先輩やロールモデルを見つける重要性
- 企業研究では「フォロー体制」も見極めよう
- よくある質問
- Q1.バディ制度とメンター制度の違いは何ですか?
- Q2.バディを組む理由は何ですか?
- Q3.バディ制度を導入するデメリットは?
- 関連記事
バディ制度とは?
バディ制度とは、新入社員や中途入社者、外国人留学生など、新しく組織に加わったメンバー(対象者)に対して、年齢や社歴の近い先輩社員が「バディ(相棒)」としてペアを組み、一定期間マンツーマンでサポートする制度です。
業務の指導だけでなく、精神的な支えとなることで、新メンバーの早期の立ち上がりと組織への適応を目的としています。
新入社員・留学生の受け入れで活用される背景
多くの企業がバディ制度を導入する背景には、人材の多様化と、それに伴うオンボーディング(受け入れ・定着支援)の重要性の高まりがあります。
特に新入社員は、右も左も分からない状態で社会人生活をスタートさせるため、業務上の疑問はもちろん、企業文化への適応や人間関係の構築など、多くの不安を抱えているでしょう。
また、グローバル化が進む現代では、文化や言語の壁を抱える外国人留学生や海外からの人材を受け入れるケースも増えています。
彼らにとっては、日本のビジネス習慣や社内ルールなど、業務以前のハードルも少なくありません。
こうした状況下で、身近な相談相手となるバディの存在は、孤独感を和らげ、安心して働ける環境を構築する上で極めて重要な役割を果たすと考えられています。
社員が業務の中でどう関わる?バディの基本的な活動内容
バディの活動は多岐にわたりますが、主に以下のような内容が挙げられます。
- 業務の進め方の指導、相談対応
OJT(On-the-Job Training)を補完する形で、より日常的できめ細かな業務の進め方やツールの使い方などを教えます。
- 社内ルールの共有
勤怠管理、経費精算、日報の書き方といった公式なルールから、部署内の暗黙の了解まで、円滑に業務を進めるための知識を伝えます。
- 人間関係の構築サポート
ランチや飲み会に誘ったり、他部署のキーパーソンを紹介したりして、新メンバーが社内で孤立しないよう手助けします。
- 精神的なサポート・悩み相談
業務上の不安や人間関係の悩みなどを気軽に話せる相手となり、精神的な支えとなります。
- 定期的な面談とフィードバック
週に1回、月に1回など定期的に面談の機会を設け、進捗の確認や目標設定、フィードバックを行います。
メンター制度やOJTとの違いは?役割や目的の違いを整理
バディ制度と混同されやすい制度に「メンター制度」と「OJT」があります。それぞれの違いを理解することで、バディ制度の特性がより明確になります。
メンター制度との違い|心理的支援と業務支援の役割差
メンター制度も先輩社員が後輩を支援する点は共通していますが、その主目的はキャリア形成や自己成長といった中長期的な視点での精神的・心理的支援にあります。
多くの場合、メンターは他部署の先輩社員が務め、直接的な業務指導からは距離を置きます。
これにより、利害関係のない立場で、キャリアパスや人間関係の悩みなど、より幅広い相談に対応しやすくなります。
一方、バディ制度は日々の業務遂行をスムーズにすることが主な目的。
同じ部署の先輩が担当することが多く、より実践的で短期的な業務サポートが中心となります。
「相棒(バディ)」という言葉が示す通り、二人三脚で目の前の業務に取り組むイメージです。
OJTとの違い|日々の仕事の中での指導との違い
OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じて仕事に必要な知識やスキルを習得させる教育手法です。
指導役は直属の上司や先輩社員が担い、具体的な業務のやり方や手順を直接的に教えます。
OJTの目的は、あくまで「業務遂行能力の向上」にあります。
バディ制度は、このOJTを補完する役割を担います。
OJTでは聞きにくいような初歩的な質問や、「こんなことを聞いたら迷惑かな」と感じてしまうような些細な悩みを解消する受け皿として機能するでしょう。
業務スキルだけでなく、社内での立ち振る舞いや人間関係の構築といった、より広範な「会社に馴染む」ためのサポートを行う点が大きな違いです。
なぜバディ制度を設けるのか?企業側の目的とは
企業がコストや手間をかけてまでバディ制度を導入するには、明確な目的があります。
定着率向上や早期戦力化への期待
最大の目的は、新入社員の離職防止と早期戦力化です。
入社後の孤立感や業務への不安は、早期離職の大きな原因となります。
身近に頼れるバディがいるという安心感は、エンゲージメントを高め、組織への定着を促します。
きめ細かなサポートによって業務習得のスピードが上がれば、それだけ早く組織に貢献できる人材へと成長してくれるという期待もあるのです。
社員同士のコミュニケーション促進・組織活性化
バディ制度は、新入社員と先輩社員という縦のつながりを強めるだけでなく、組織全体のコミュニケーションを活性化させる効果も期待できます。
バディになった先輩社員は、新人を指導する過程で自身の業務を見つめ直したり、マネジメントの視点を学んだりする機会を得られます。
また新入社員が他部署のバディと交流することで、部門間の連携がスムーズになることもあるでしょう。
こうしたナナメの関係性が増えることで、組織に一体感が生まれ、風通しの良い企業文化の醸成につながります。
バディ制度を導入するデメリットとは?注意すべき4つの課題
多くのメリットが期待されるバディ制度ですが、運用方法を誤ると様々なデメリットが生じます。
ここでは、現場で起こりがちな4つの課題を解説します。
バディ側の業務負担が重くなりがち
新人対応が“追加業務”と感じられると、疲弊やモチベーション低下の原因になる恐れがあります。
特にエース社員ほど任命されやすく、プレッシャーも大きくなりがちです。
相性による影響が大きい
どんなに制度が整っていても、人間同士の相性が悪ければうまくいきません。
合わない相手に遠慮して相談できない…そのようなケースも起こりうるでしょう。
属人化・形骸化のリスク
制度設計が曖昧だと、「指導がうまい人だけが機能する」「気づけば何もやっていない」など、形だけの制度になる恐れも。
やらされ感が生まれる
「目的が伝わっていない」「評価にも反映されない」状況では、バディ側も新人側も“やらされている”と感じやすいでしょう。
バディ制度の効果を最大化させるための運用の工夫
前述したデメリットを回避し、バディ制度を有効的に活用するためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。
バディ制度の目的と役割を明文化する
まず、「何のためにバディ制度を導入するのか」という目的を明確にし、関係者全員で共有することが重要です。
定着率向上、早期戦力化、組織文化の浸透など、具体的なゴールを設定しましょう。
その上で、バディと新入社員、それぞれの役割と責任範囲、活動期間、報告のフローなどを明文化したガイドラインを作成します。これにより、「何をすれば良いのか分からない」という状態を防ぎ、活動の属人化や形骸化を抑制できます。
定期的な面談・フィードバックで孤立を防ぐ
バディと新入社員のペアだけに任せきりにするのではなく、人事担当者や上司が定期的に双方と面談する機会を設けることが重要です。
これにより、ペア内で起きている問題(相性の問題、指導の停滞など)を早期に発見し、介入することができます。
バディ役の社員が抱える悩みや負担を聞き出し、サポートする体制も不可欠!
両者とも孤立させない仕組みが、制度を安定的に運用するカギとなります。
上司や教育担当と連携したトライアングル支援
最も効果的な運用方法の一つが、「バディ」「直属の上司」「人事・教育担当」が三位一体で新入社員を支える「トライアングル支援体制」を構築することです。
- ◾️ バディ:日常的な業務の相談、精神的なサポート
- ◾️ 上司:業務上の目標設定、パフォーマンス評価、キャリア指導
- ◾️ 人事:制度全体の設計・運用、バディへの研修、問題発生時の介入
この3者が定期的に情報交換を行い、それぞれの視点から新入社員の状況を共有し、連携して育成方針をすり合わせることで、より多角的で一貫性のあるサポートが可能になります。
バディ制度を導入している企業
実際にバディ制度を導入している企業を見てみましょう。
株式会社LITALICO
企業概要はこちらから!
株式会社LITALICO
株式会社ラクス
企業概要はこちらから!
株式会社ラクス
Sansan株式会社
企業概要はこちらから!
Sansan株式会社
共通する成功ポイント
- ・制度の事前研修(バディ対象者向け)
- ・評価制度への反映(育成への貢献を評価)
- ・フィードバックループ(人事との連携や改善)
不安を感じたらどうすればいい?制度との付き合い方と企業選びの視点
新入社員の立場として、バディ制度に不安を感じることもあるかもしれません。
そんな時の心構えと対処法を紹介します。
「同期がいない=不安」と決めつけない考え方
特に中途採用で入社をする場合は、同期がいないこともしばしば。
心細く感じることもあるでしょう。
しかしバディ制度は、そんな状況だからこそ用意されたセーフティーネットでもあります。
バディ制度とは、「上司とは異なる、頼れる存在が必ずいる」ことであると前向きに捉えましょう。
同期という横のつながりではなく、バディというナナメのつながりを築くチャンスだと考えてみてください。
信頼できる先輩やロールモデルを見つける重要性
バディはあくまで会社が用意した制度上の一つの関係です。
もしバディとの相性が合わないと感じても、過度に思い悩む必要はありません。
大切なのは、あなた自身が「この人のようになりたい」「この人に相談したい」と思えるロールモデルや、信頼できる先輩を社内で見つけることです。
バディ制度をきっかけに、積極的に他の社員ともコミュニケーションを取り、自分なりのサポートネットワークを築いていきましょう。
企業研究では「フォロー体制」も見極めよう
これから就職・転職活動をする方は、企業の「フォロー体制」を事前に見極めることが重要です。
- 採用サイトや求人票の確認
「メンター制度」「ブラザー・シスター制度」など、具体的な制度名や内容が記載されているかチェックしましょう。
志望企業の求人票にはどのようなサポートがあるのか具体的に書かれていますか?
- 担当エージェントに実際の運用状況を聞き出すのもおすすめ
制度が形骸化していないか、どんな先輩社員がバディにつくことが多いのか、現場のリアルな情報をエージェント経由で把握しておくと、入社後のギャップを減らすことができるかもしれません。
- 面接での逆質問
面接は、企業を見極める絶好の機会です。
以下のような質問をしてみるのも良いでしょう。
「入社後、業務に慣れるまでどのようなサポート体制がありますか?」
「御社では、若手社員の育成においてどのような点を重視されていますか?」
「もしよろしければ、〇〇様(面接官)が新入社員だった頃、どのように業務を覚えていかれたかお伺いできますでしょうか?」
よくある質問
Q1.バディ制度とメンター制度の違いは何ですか?
主な違いは目的と役割です。
バディは「日常的な業務サポート」が中心で、同じ部署の先輩が担当し、早期戦力化を目的とします。
一方、メンターは「心理的支援・キャリア相談」など、より広範囲で中長期的なフォローが目的であり、他部署の先輩が担当することが多いです。
Q2.バディを組む理由は何ですか?
新しく入社した社員が抱える業務上・精神上の不安を和らげること、業務習得のスピードを上げ早期に活躍してもらうこと、そして組織文化へスムーズに適応し、定着を促すことなどが主な理由です。
Q3.バディ制度を導入するデメリットは?
バディ役の社員への業務負担の偏り、新入社員との相性による指導品質のばらつき、教育内容が属人化しやすく、制度の目的が共有されないまま運用されることで形骸化してしまうリスクなどが挙げられます。